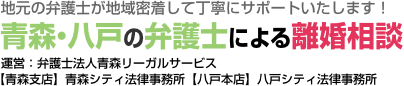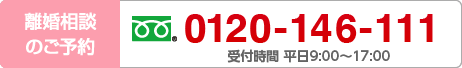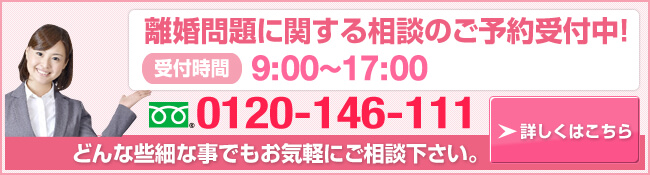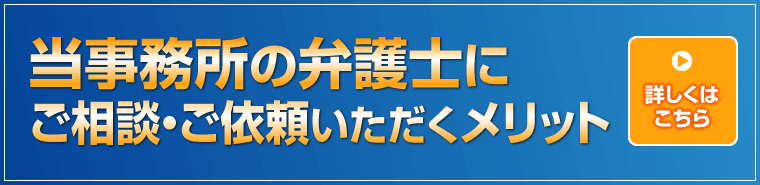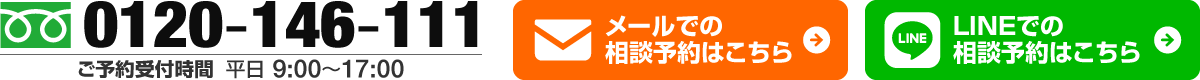1 年金分割制度とは?
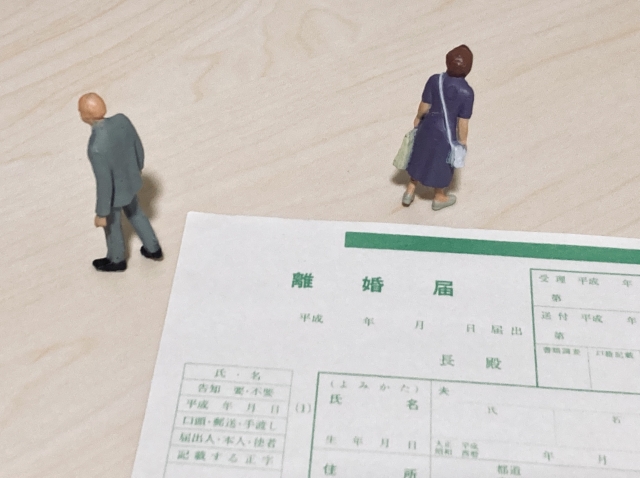
年金分割制度とは、離婚の際に、厚生年金の保険料の納付記録を夫婦で分割する手続きです。
婚姻期間中の保険料の納付記録は、夫婦の協力のもと培われてきたものであるといえます。
しかし、離婚した場合、何もしなければ、実際に保険料を納付した側のみがこれに応じた年金を受け取れることになりかねません。
このことは、特に夫婦の一方が専業主婦(夫)であるなど、夫婦の収入に格差がある場合に特に問題になります。
このような場合において、保険料の納付記録が均等になるように分割し、将来、これに応じた年金を受給できるようにするのが年金分割です。
2 熟年離婚における年金分割制度
年金分割は婚姻期間中に納付してきた保険料を分割する手続きですから、婚姻期間の長い熟年離婚であるほど対象となる期間・保険料が大きく、実際の年金額への影響も大きいということになります。
また、年金の受給年齢に近い熟年離婚のケースであれば、離婚後の生計に直結し、離婚への足掛かりとなる制度といえます。
3 年金分割の手続きの流れ
年金分割には、合意分割と3号分割の2種類の手続きがあります。
(1)合意分割
合意分割とは、夫婦の合意に基づき年金分割を行う場合の手続きです。
手続の流れとしては、まず、年金事務所に対し所定の請求書を提出し、年金分割のための情報通知書を取得します。
そのうえで、離婚を協議で進める場合は、年金分割について話し合って合意をします。
その後、二人で年金事務所に行って手続きを行うか、公正証書を作成のうえ、公正証書を使用して単独で手続きを行うことになります。
また、協議による合意が難しい場合は、家庭裁判所の調停・審判を申立てたうえで、調停調書・審判書を使用して単独で手続きを進めることになります。
なお、合意分割においては、分割の割合も2分の1を上限として合意で決定することが可能ですが、夫婦が平等になるように2分の1とするケースがほとんどです。
(2)3号分割
3号分割とは、第3号被保険者であった場合、すなわち厚生年金の加入者である配偶者に扶養されていた場合に利用できる年金分割の制度です。
合意分割との大きな違いは、配偶者との合意は不要であり、原則として、離婚後に、年金事務所にて単独で手続きをすることが可能というところにあります。
ただし、3号分割は平成20年(2008年)4月に開始した制度であり、分割の対象となるのもこの平成20年(2008年)以降の保険料の納付記録に限定されます。
4 熟年離婚における年金分割の注意点
熟年離婚においては、3号分割の対象となる平成20年(2008年)より前から婚姻をしていたケースが想定されます。
この場合、最大限の年金分割を行うためには、協議や調停などを行ったうえで合意分割をする必要が出てくる可能性があります。
また、熟年離婚では長い婚姻期間を通じた厚生年金保険料の納付記録を比較することになりますので、相手方に無職期間や自営業者の期間がある場合などは、年金分割のメリットを慎重に判断する必要があります。
5 熟年離婚に関するお悩みは弁護士にご相談ください
これまでの生活を大きく変えることになる熟年離婚に踏み切ることには不安もあるものと存じます。
そのため、熟年離婚については、年金分割などの制度も踏まえた専門家のサポートを受けながら進めることをお勧めいたします。
熟年離婚に関してお悩みでしたら、まずは一度、当事務所までご相談いただければと存じます。