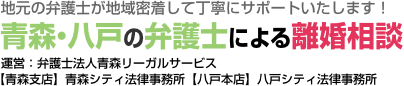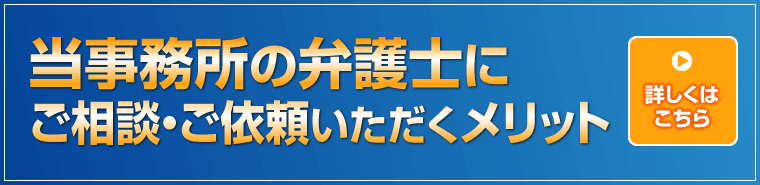親権者判断の考慮要素のひとつとして、面会交流への寛容性が挙げられますが、実際のところは、面会交流の内容が親権者判断にどの程度影響を及ぼすのでしょうか?
近日、この論点を巡る離婚裁判で、別居している夫婦が長女の親権を争っていたところ、最高裁判所が父の上告を受理しない決定をしたことで、母を親権者とした第二審判決(東京高等裁判所平成29年1月26日判決)が確定したことが報じられました。
この事件は、第一審判決(千葉家庭裁判所松戸支部平成28年3月29日判決)が、父の提案した面会交流の内容などを評価して、父を親権者とするという、これまでにはなかった判断を示していたため、注目を集めていました。
第一審判決や第二審判決によると、本件の事案は次のとおりです。
夫婦は、平成18年に結婚し、長女を設けましたが、価値観や経済観等の違いから口論をすることがあり、平成21年頃からは夫婦関係が険悪になり、けんかにより警察官を呼ぶ騒ぎに発展したこともありました。
そのような中、母は、父に無断で、当時2歳4か月の長女を連れて自宅を出て、実家に戻りました。
その後、父と長女の間では、面会交流や電話での会話による交流が行われていましたが、平成23年9月に行われた面会交流を最後に、父は長女と会っていないといった状況でした。
第一審判決は、①母は、父に無断で長女を連れ出して約5年10か月間長女を監護していたが、その間、長女と父との面会交流には合計6回程度しか応じておらず、今後の面会交流も月1回程度を希望している、②他方で、父は、これまで長女を取り戻すべく数々の法的手段に訴えてきたがいずれもうまくいかず、長女との生活が実現した場合には、整った環境で周到に監護する計画と意欲を持っており、長女と母の交流については、年間100日に及ぶ面会交流の計画を提示している、とした上で、③長女が両親の愛情を受けて健全に成長することを可能とするためには、父を親権者とすることが相当である、と判断しました。
第一審判決では、面会交流の内容や積極性といった要素を重視して、親権者を判断していると見受けられるところです。
このように面会交流の内容を重視する考えは、「フレンドリー・ペアレント・ルール」や「寛容性の原則」と呼ばれることがあります。
これは、面会交流などを通じて他方の親との交流により良好な関係を保つことが子の人格形成のためには重要であるから、より子の面会交流を肯定的・積極的に考えている親が親権者になることが、より子の福祉に資するとする考え方です。
これは近年提唱された新しい考え方と言えます。
しかしながら、第二審判決では、第一審判決を変更して、母を親権者としました。
第二審判決では、まず、親権者の判断方法を提示しています。
つまり、親権者の判断に当たっては、これまでの子の監護養育状況、子の現状や父母との関係、父母の監護能力や監護環境、監護に対する意欲、子の意思、その他子の健全な育成に関する事情を総合的に考慮して子の利益の観点から親権者を定めるべきであるとしています。
そして、第一審判決が重視した面会交流の内容については、考慮要素の一つではあるが、それだけで子の健全な育成や子の利益が確保されるわけではないから、他の諸要素より重要性が高いとも言えないとしています。
その上で、長女の出産後は、母が長女の主たる監護者であったこと、長女は現在も安定した生活を送っており母子関係にも特段の問題がないこと、父母の監護能力や監護環境については決定的な差はないこと、長女を転居・転校させて現在の監護養育環境を変更しなければいけない必要性がないこと、といった事情を総合的に考慮し、長女の利益を最も優先して考慮すれば、母を長女の親権者にするのが相当であると判断しました。
また、第一審判決で評価された父が提案した面会交流の計画については、片道2時間半かかる距離の中、小学生の長女が年間100日の面会交流の度に父母の自宅を往復することになれば、身体の負担のほか、学校行事への参加や友達との交流等にも支障が生じるおそれがあると指摘されています。
そのほか、第二審判決では、母が長女を一方的に連れ去ったことや、母が長女と父との面会交流を拒んだことについても、次のように説明しています。
長女を連れ去ったことについては、当時長女はまだ幼く、業務で多忙な父に長女の監護を委ねることは困難であり、夫婦関係が険悪な状況で、長女の今後の監護について協議するのも困難であったと指摘されています。
また、面会交流を拒んだことについては、母が面会交流を拒んだのは、離婚後片親と会えなくなる子どもの現状を特集したテレビ番組に、父が提供した面会交流時の長女の映像が放映され、これに衝撃を受けたためであると指摘されています。
そのため、いずれの事情によっても、母が親権者にふさわしくないとは認め難いとされています。
このように第二審判決では、子の利益の観点から、様々な事情を総合的に考慮して親権者を判断しているところです。
そして、第一審で重視されていた面会交流の内容については、他の事情と同じくあくまで一要素として考慮するという立場を取っており、第一審判決とは、立場を異にしていると言えます。
このような判断の方法は、これまでの裁判実務の傾向を踏襲したものといえます。
最高裁判所は、今回の事件で、これまでの裁判実務の傾向に沿った判断を示した第二審判決を追認した形となります。
そのため、親権の判断に当たっての裁判実務の考えには今後も大きな変化はなく、第二審判決が示したような諸要素を考慮して、親権者を判断する手法が取られていくものと考えられます。
そうすると、子どもの監護の機会を持つことが少ない父側が親権を獲得することには、どうしても高いハードルがあります。
しかし、今回の裁判では、面会交流の内容も親権判断の考慮要素の一つとされています。
また、第二審判決でも、子どもを連れて出て行き、父と長女との面会を拒んだ母側にも事情があることが指摘されているところであり、決して子どもの連れ去りや一方的な面会拒否を許容するものではありません。
そのため、子どもを連れ去り、面会交流を特に理由もなく拒絶しているようなケースでは、親権者として不適格と判断されてしまう場合もあり得るかと思います。
(弁護士・山口龍介)